愛大オープンカレッジ

2025年度の愛大オープンカレッジは終了しました!ご参加ありがとうございました!
講座概要
8/25(月)
-

[Mon-1] 大谷選手も使った、夢を叶えるマンダラチャート
講師/中野 慶昭
密教の曼荼羅を基に、日本人の経営コンサルタントが開発したものが「マンダラチャート」だと言われています。ビジネスの世界で目標達成のツールとして使われているマンダラチャートですが、実は、あの大谷選手も目標達成を目指して16枚も書いていたそうです。
皆さんも自分の夢を実現するためのツールとして、マンダラチャートを一緒に描いてみませんか。 -

[Mon-2] 知らないと損をする情報セキュリティ
講師/日坂 彰
日本では初めて個人がインターネットを使えるようになってから約30年が経ちました。インターネットが社会的基盤となり、ICT(情報通信技術)の利活用により私たちの生活の利便性は飛躍的に向上しました。その一方で、新しい技術を悪用する行為や犯罪も急増しています。属性や年齢に関係なく、ICTデバイス(スマートフォンやPC等)やサービスを利用する人は誰でも、情報セキュリティの素養は必須の時代となりました。いまいちど情報セキュリティの基本を見直してみましょう。 -

[Mon-3] 宝くじで確率を考えてみよう
講師/大屋 伸彦
公営ギャンブルは過去のレース結果から、ある程度は勝敗を予測することができます。宝くじは過去の抽選結果のデータから将来の当選番号を予測することはできません。宝くじは当選本数が決まっているため、連番での購入枚数によって当選確率が変動します。宝くじを題材として、確率的にものごとを捉える方法についてみなさんと学んでいきたいと思います。※公営ギャンブルや宝くじを推奨するものではございません
-

[Mon-4]マンホール神経衰弱,セットになるのはどれだ?
講師/梶原 健嗣
いま,日本では多くの日本自治体がデザインマンホールを作っています。それらは地域のシンボルを描き出したものが多く,創意工夫に富んでいます。自治体によっては複数のデザインマンホールがありますが,この講座では,それを「神経衰弱」のように,セットを当ててもらうクイズにチャレンジしてもらいます。「このデザインは何を意味しているんだろう? 関係あるのはどこ?」と考えるなかで,地域の思い・創意工夫を読み当ててください。
-

[Mon-5]「先住民文化から学ぶSDGs」
講師/岡庭 義行
漫画やアニメで人気を博した『ゴールデンカムイ』には,北海道の先住民族であるアイヌの人々の生活と文化が丁寧に描かれていると言われています。アイヌの人々は,自然への感謝と生命に対する敬いの気持ちを大切にしながら,豊かな文化を連綿と育んできました。この講座では、自然との共生をテーマとして,北の地域に暮らす先住民たちの自然観を通して,皆さんと一緒にSDGsについて考えてみたいと思います。
8/26(火)
-

[Tue-1]炎上するのはなぜ?~『ちば、大好き!』で学ぶココロのしくみ~
講師/中村 博子
SNSでの炎上や、少し違うだけで仲間はずれにされる…。どうしてそんなことが起きるのでしょう?千葉県内で実際にあった出来事をもとに、「黒い羊効果」や「スケープゴート」など、排除の心理メカニズムをやさしくひもときます。人を傷つけてしまう心の背景を知り、「ちば、大好き!」=人を思いやり、自分も大切にする気持ちの大切さについて、心理学の視点から一緒に考えてみましょう。
-
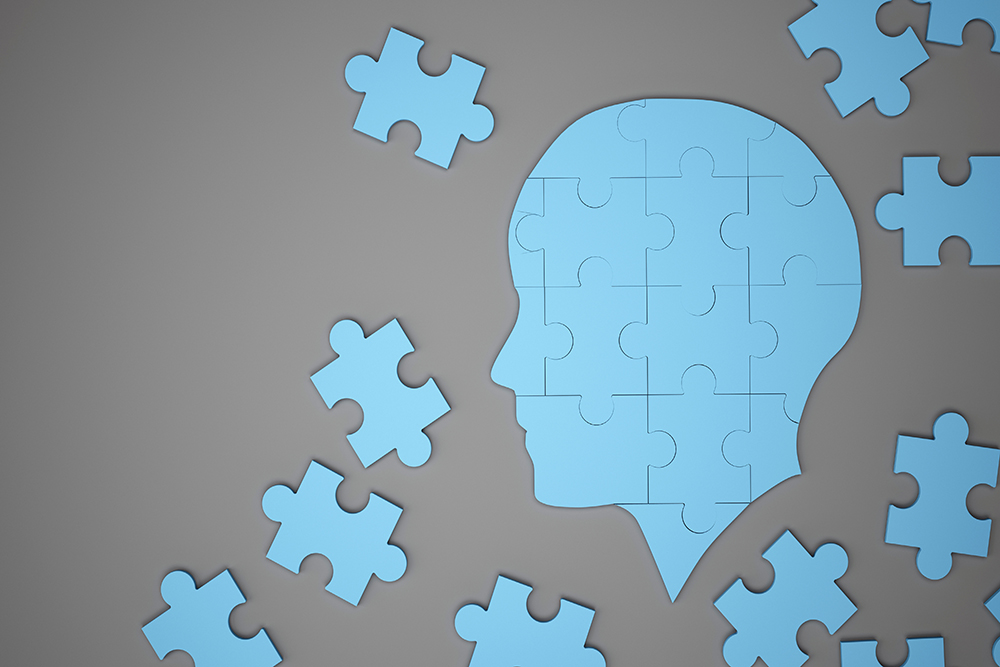
[Tue-2] ちばの人は明るく大らかな性格? ~心理学から県民性を考える~
講師/原島 雅之
性格は人それぞれの個性として十人十色でありつつも、「〇〇の人々はみな△△だ」というように、ある集団に共通の特徴があるように思われることもあります。その中で、いわゆる「県民性」と呼ばれるものがあります。ためしに千葉の県民性で検索してみると、「明るく大らか」、「さばさばとした(浜っ子気質)」などのフレーズがでてきます。果たして千葉県の人々は本当にそうなのでしょうか。この授業では心理学的視点から県民性について考えてみたいと思います。
-

[Tue-3] 食べてはいけないもの~ちば編~
講師/岡庭 義行
私たちの食生活には,食べられるものと食べられないもの以外に「食べられるが食べてはいけない」と考えられているものがあります。このような「食べてはいけないもの」の多くは,時代や地域によって異なることが知られています。この講座では,私たちが暮らす“ちば”において,歴史的に食べてはいけないと考えられてきたものを探しながら,その理由や背景をみなさんと一緒に考えてみたいと思います。 -

[Tue-4] 福祉の視点でちばの未来をデザイン!~高校生のための地域づくり入門~
講師/鈴木 智子
ちばの福祉課題や強みを共有したうえで、「こんな未来にしたい!」というアイデアをみんなで考えます。希望する未来を実現するため、自分にできること、友達やまわりの人と力を合わせてできること、行政にやってほしいことを、グループで話し合いながら一緒に見つけ、世界にひとつしかない「ちばみらいマップ」をつくっていきます。
-

[Tue-5] 地元で育つ“食”の力~ちばの農林水産業と未来のつながり~
講師/呉 鳶
千葉県は首都圏に位置しながらも、多様な農林水産資源に恵まれた地域です。本講義では、千葉県の農業・林業・水産業の現状や課題に加え、生産から消費までをつなぐ地域フードシステムの取り組みについて紹介します。持続可能な食の未来を考えるために、地域資源の活用や地産地消の推進、フードロス削減など多角的な視点から学びます。
8/27(水)
-

[Wed-1]その呼び名に歴史あり ~地名と苗字で見るちばの歴史~
講師/佐久間 直人
自分が暮らす町の地名や自分の苗字は、いつも当たり前のように使っていて、深く考える機会はなかなか無いでしょう。それらを気に入っておらず、もっと他の名前が良かったのにと思ったこともあるかもしれません。しかし、地名や苗字の由来や歴史を知ると、名前に愛着がわいてきますし、いつの間にか勉強にもなるのです。千葉県の例を通して、苗字や地名について調べる楽しさを体験しましょう!
-

[Wed-2] 地図で読み解く、ちばの自然と産業
講師/栗林 慶
千葉県は、海・川・台地・平野といった多様な自然環境をもち、それが漁業・農業・工業など多彩な産業の発展に大きな影響を与えてきました。本講座では、地図や地形図を手がかりに、千葉の自然環境と産業の関わりを読み解きます。地域の特徴を「地理学の目」で見ることで、身近な風景の奥にある地理的背景や社会のしくみに気づくことができるでしょう。
-

[Wed-3] 和棉のはなし~私たちの身の回りにある布について考えてみよう!
講師/山﨑 寿美子
皆さんは、自分の着ている服の素材が何か、それがどこでどうやって作られたのかについて、考えたことはありますか?かつて日本には、風土に適した在来種の棉がありましたが、今では綿の国内自給率はほぼ0%で、流通する綿は海外からの輸入に頼っています。しかし、大量生産・大量消費の問題点が明るみになるにつれ、モノを作る人、使う人、それぞれの暮らしが循環していく仕組みに、改めて光が当てられています。今回は、循環型社会の実現に向けた取り組みの一つとして、日本で作られている棉について、皆さんと一緒に考えます。
-

[Wed-4]ちばの歴史遺産~日本の原点を探る
講師/太田和 良幸
千葉県は、縄文時代の人々の住居の跡を示す遺跡である「貝塚」を日本で最も多く有する地域であり、当時の日本の中心地であったと考えても過言ではありません。多くの人々が定住し、平和で豊かな文化が築かれていました。その後の古墳時代においても、千葉県には日本最多の前方後円墳が存在することから、この地域が長く栄えていたことが伺えます。こうした歴史を通じて、ちばの特色を地理的、歴史的、文化的な視点から考察していきます。
-

[Wed-5] 江戸時代のちばの名産品~今はないモノ・今もあるモノ
講師/中村 塑
みなさんは「ちばの名産品」と聞いて何を思い浮かべますか?野田や銚子などでつくられ、生産量全国ナンバーワンの「醤油」?八街を中心に県内各地で栽培されている「落花生」?木更津・富津など東京湾岸で養殖されている「のり」?マスコットキャラクターで知られる船橋の「梨」?などなど、人によってさまざまであると思います。この講義では江戸時代と現代のちばの名産品を比較します。意外な発見があること間違いなし!
8/28(木)
-

[Thu-1]そのクセ、好き嫌い、治ります ~行動変化の心理学~
講師/佐久間 直人
誰しも何らかのクセや好き嫌いなど、「自分ではどうしようもない」と感じる傾向をもっているものです。いわゆる貧乏ゆすりなどのわかりやすいクセだけでなく、怒りっぽい、緊張しやすい、だらけてしまうなど、性格だと思っていることの多くも実は一種のクセなのです。この授業では、クセや好き嫌いができる仕組みである「条件づけ」という心理学の有名なテーマを解説します。嫌なクセを治し、良いクセを身につけるヒントにしてください。
-

[Thu-2] 「自分」について知るための心理学
講師/原島 雅之
皆さんは「自分」のことをどれだけ知っているでしょうか?生まれてからずっと自分自身のことを最も間近で観察してきたと考えれば、皆さん以上に「自分」について詳しい人はいないように思えます。しかしその一方で、実際にどのような人か聞かれるとなかなか答えられないのではないでしょうか。この講座では、心理テストの体験などを通して、皆さんが自分自身のことをよりよく知るきっかけになるようなお話をしたいと思います。
-

[Thu-3]こころが疲れたあなたへ~アートセラピーの体験~
講師/中村 博子
みなさんは、こころが疲れたとき、どのように元気を取り戻しますか?
人に話を聴いてもらうこともいいですね。でも、どう話していいかわからないとき、臨床心理では「アートセラピー(芸術療法)」というものがあります。今回はそのなかのひとつ、スクイッグル法を体験して、こころが元気になり人とつながる体験をしてみませんか?自分の無意識の内面を開放しましょう。絵の苦手な人でも大歓迎です。 -

[Thu-4] アロマテラピーの楽しみ方
講師/市川 遥夏
アロマテラピーとは植物の香りを利用して心身を癒し、リフレッシュさせる自然療法です。様々な効果を持つ精油を組み合わせることで、心身をリラックスにしたり、QOL(生活の質)を高めたり、家事を楽にさせるなど、普段の生活改善や健康維持を増進させる働きがあります。近年では、コロナ禍でもアロマテラピーの活用に注目され、COVID-19が原因で起こる不安やストレスの予防など精油による身体のコンディションの整え方を解説していきます。
-

[Thu-5] 観光の「わくわく」と「がっかり」~私たちは観光に何を求めているのか
講師/𠮷元 菜々子
みなさんは観光が好きですか?ガイドブックやネットを見ながら旅行の計画を立てるのは、とてもわくわくしますよね。ところが実際に観光地に行ってみると、満足することもあれば、思っていたのとは違ってがっかり、なんて経験もあるかと思います。私たちが感じるこの「わくわく」や「がっかり」は、一体どこからくるのでしょうか。この講座では、私たちが観光で感じる気持ちの正体について、観光学の視点から考えていきます
8/29(金)
-

[Fri-1]これであなたもコミュニケーションの達人
講師/清水 聖子
話が上手、説得力がある、なぜかあの人と話すと楽しい・安心する、といったいわゆるコミュニケーション上手な人の特徴はなんでしょう?他国の人と比べて日本人はコミュニケーションが下手?なぜでしょう?本当にそうなの?自分の意見や気持ちをどうすればうまく伝えられるのかな?など、コミュニケーション論という学問の領域からコミュニケーションについてあれこれを見ていきたいと思います。
-

[Fri-2]その日本語、本当に大丈夫?
講師/部田 和美
国内外には何百万という日本語学習者がいます。彼らはどんな勉強をしているのでしょうか? 日本語の学習は国語学習とは異なり、言葉を話すためのルールを学ぶことです。本講義では、日常会話やメディア、SNS等で実際に使われている日本語を例に挙げ、私たちが意識することなく自由に話している日本語の決まり事を探り、その特徴を理解するとともに、日本人の思考や文化が言葉にどう影響しているのかについても考えてみます。
-

[Fri-3]人間はお金とどう付き合ってきたのか ~お金の歴史を知る~
講師/中村 塑
昨年(2024年)、日本では2004年以来20年ぶりに新紙幣が発行されました。当たり前のことですが、旧紙幣と新紙幣は肖像画やデザインなどは異なるものの、どちらも紙でつくられています。世の中にはさまざまなものがありますが、なぜ紙がお金になったのでしょうか?また、一般的に人間はより多くのお金を欲します。それでは億や兆レベルのお金があれば何でも欲しいものは手に入るのでしょうか?以上のような問題を歴史的に考えてみます。
-
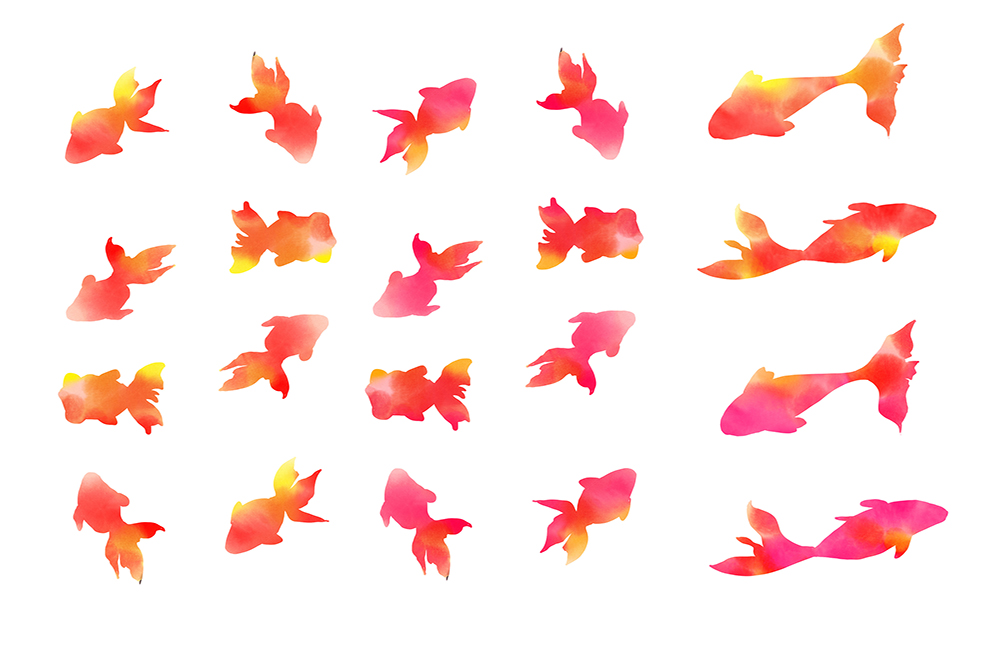
[Fri-4] アートな金魚
講師/太田和 良幸 学長
金魚と聞くと、金魚すくいの金魚を思い出す人が多いかもしれません。しかし実は、金魚は人間が生き物を使って創造した「アート作品」なのです。他の動植物の中にも、人が手を加えて創造したものが多数ありますが、金魚ほど極端にデフォルメされた生き物はいません。錦鯉や盆栽よりもユニーク極まりない金魚の魅力を見つけてみましょう。
金魚の飼育方法の基本も学べます。希望者には、金魚の王様「らんちう」をプレゼント。金魚すくいの金魚ではない本格的な金魚(アートな金魚)を鑑賞して、人間の創造力の豊かさを実感してみましょう。 -

[Fri-5] 「カーレット」って知ってる?
講師/太田和 良幸 学長
カーレットは、氷上で行うカーリングをテーブル上で身近に行えるように工夫し、千葉県で考案された競技です。競技者が一緒になって楽しみながら、コミュニケーションを深めていくことを目的としています。「コミュニケーションと人間の五感を培うことを多く含んだ思考的・知的ゲーム」と言われています。カーレット競技に親しむことを通じて、考える力、協同する力が養われます。初心者大歓迎です。ルールから簡単に学ぶことができます。特別な運動能力は必要ありません。普段着で参加してください。愛国学園大学のカーレット部員とともに、カーレット競技を楽しみましょう。
参加申し込み
参加申し込みはこちらから
開催概要
申込方法
参加申し込みは、以下の参加予約フォームからお申込みください。
※参加費は無料です。
※1コマから受講できます。(各講座先着順20名まで)
※1人何講座でもご参加いただけます。
申込締切
各講座、開講日の2日前まで
会 場
愛国学園大学(千葉県四街道市四街道1532)
1号館 2階A204視聴覚室・A205情報処理室
対 象
高校生 生徒の保護者の方 学校関係者の方
注意事項
- 各講座先着20名までとさせていただきます。
- お申込み人数が定員を超えた場合、受講できない旨をご連絡します。
- 体調不良の場合には、参加を見合わせてください。
- 愛国学園大学事務局及び講師等の都合により、講座の開講を中止することがあります。予めご了承ください。
- 受講希望者が最小開講人数に達しない場合は、原則として講座は開講中止となります。
- その場合は開講2日前までに各お申込み先より電話またはメールにてご連絡いたします。
- 申し込み後、受講をキャンセルされる場合は、お問合せ先までご連絡ください。
(愛国学園大学 公開講座係 TEL 043-424-4433、MAIL soumu"@"aikoku-u.ac.jp)
受講上の注意
- 前の授業で教室を使用している場合は、その授業が終わるまで教室には入室しないでください。
- 建物内では他の講義の迷惑になるような行為はご遠慮ください。
- 教室内での食事・喫煙はご遠慮ください。
- 受講中の携帯電話などは電源を切るか、マナーモードに設定してください。
- 講師の許可がある場合を除き、講座の録音・録画・写真撮影はお断りします。講座資料においても講師の許可なく複製・再配布・デジタルデータ化した上でのインターネットへのアップロード行為はおやめください。
- 盗難等について、本学は一切責任を負いません。
- 本学の駐車場は利用できませんので、来校には公共交通機関をご利用ください。
- 原則として受講は申込み者ご本人に限ります。代理の方や事前にお申込みいただいたご家族以外の方は受講できません。
「愛大オープンカレッジ」
主 催
愛国学園大学
後 援
千葉県教育委員会
四街道市
四街道市教育委員会